知識編:インセクトホテル
インセクトホテルとは?生物文化多様性とは?この教材の基本的な考え方について説明します。
虫が土の中から出てくることを意味する「啓蟄」という言葉があります。これは一年を二十四に区分する二十四節気という伝統的な暦の一部です。今の暦の3月5日ごろにあたります。土の中から出てくるというのはなぜかといえば、冬ごもりをしていたからです。昔の人たちは、多くの虫が土の中などで冬を越すことを、観察してきちんと知っていたことがわかりますね。
二十四節気のほかに、一年を七十二に区分する七十二候という暦もあります。二十四節気で虫に関連するのは「啓蟄」だけですが、七十二候には「啓蟄」と同じ意味である「蟄虫啓戸」(3月5日ごろ)のほかに、「蟄虫坏戸」(9月28日ごろ)という暦もあります。「蟄虫坏戸」は一般に「むしかくれてとをふさぐ」と読みます。冬の訪れに備えて、虫が土の中に潜り込んで戸締りをするころ、という意味です。実際には9月28日には虫たちはまだ冬眠しないと思いますが、この時期から次第に虫が冬ごもりに入っていくと考えられていたに違いありません。
さて、七十二候にはいろいろな虫が登場してきます。次の七十二候は、いつごろを指すと思いますか。
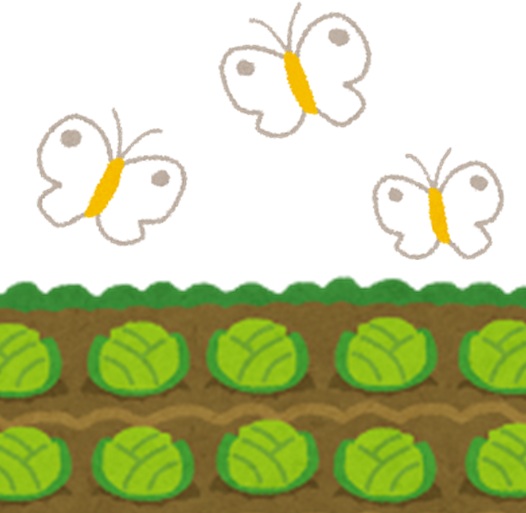

インセクトホテルとは?生物文化多様性とは?この教材の基本的な考え方について説明します。

身近なはずの虫が,いつの間にか減っている⁉人間活動と地球環境の変化との関係を,虫をきっかけに見つめ直してみましょう。