知識編:インセクトホテル
インセクトホテルとは?生物文化多様性とは?この教材の基本的な考え方について説明します。
「虫」という漢字は、もともと「マムシ」の意味で使われていました。では昆虫はどう表現していたかというと「蟲」という字を使っていました。「虫」が三つ重なった形です。ここから「蟲」の豆知識を一つ紹介しましょう。
実は「蟲」という文字は、昆虫だけでなく、いろいろな生き物を指すことができました。例えば「羽蟲」は羽の生えた生き物、つまり鳥を意味します。現代なら「羽虫」は「ハムシ」と読んでコバエなどを連想しますね。では「毛蟲」はといえば、毛が生えた生き物をいいますから、多くの哺乳類が「毛蟲」だということになります。猫も犬も「毛蟲」です。現代の「ケムシ」とは全く違う意味になります。

さて、人間は「毛蟲」に入るのでしょうか。確かに人間には頭髪などの毛が生えています。しかし、残念ながら人間の体毛は全体を見れば非常に薄いので、「毛蟲」の仲間には入れてもらえません。人間はしばしば「裸蟲」と呼ばれます。ハダカなのです。
このように、「蟲」という漢字は虫以外の生き物の意味でも広く使われていました。現代でも虫偏の漢字には昆虫以外のものがたくさん含まれています。蛇(へび)、蛙(かえる)、蛤(はまぐり)、蠍(さそり)、虹(にじ)……「虫」という文字の意味する範囲は、昆虫だけではないのです。
もちろん、これは「虫」あるいは「蟲」という漢字の話であり、「むし」、つまり昆虫の話ではありません。では日本語の「むし」はどうでしょうか。昆虫だけを意味しているでしょうか。さきほど登場した「マムシ」というヘビは、実は日本でもかつて「真虫」と書いていましたから、「むし」もやはり昆虫だけとは言えなさそうです。例えば、日本語の「むし」は「泣き虫」や「弱虫」、「本の虫」など性格を表すとき、特に悪口を言うときにも使われます。また、「虫食い算」や「虫歯」など、実際の虫が悪さをしたわけではないときにも、穴があると虫のせいだと言われます。「むし」にとっては濡れ衣のような言葉が多いですが、それだけ虫が人々にとって身近な存在だったとも考えることができそうです。
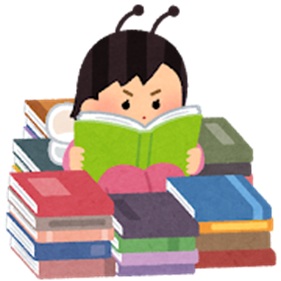
非常に身近な存在である虫は、俳句にもたくさん登場します。
しずかさや岩にしみいる蝉の声 松尾芭蕉(奥の細道)
やれ打つな蝿が手をすり足をする 小林一茶(八番日記)
松尾芭蕉はセミの声を詠い、小林一茶はハエの動きを見つめています。昆虫があまり好きではない人でも、セミの声を聞けば夏だと感じるでしょうし、ハエがまるで人のように手や足をすり合わせる姿を見たことがある人が多いのではないでしょうか。虫は私たちにとって季節を感じさせたり、日常の生活の親しい(あるいは厄介な)隣人であったりする身近な存在であることが、このような有名な俳句からもうかがえます。
以上に、言葉の世界の虫を見てきました。虫のつく漢字、虫のつく言葉を見つけたら、昆虫だけではない言葉の世界の虫に思いをはせてみてください。

インセクトホテルとは?生物文化多様性とは?この教材の基本的な考え方について説明します。

身近なはずの虫が,いつの間にか減っている⁉人間活動と地球環境の変化との関係を,虫をきっかけに見つめ直してみましょう。